| 1. |
|
| 1-1. |
|
| 1-2. |
|
| 1-3. |
|
| 1-4. |
|
| 1-5. |
|
| 1-6. |
|
| |
|
| 2. |
|
| 2-1. |
|
| 2-2. |
|
| 2-3. |
|
| 2-4. |
|
| |
|
| 3. |
|
| 3-1. |
|
| 3-2. |
|
| |
|
| 4. |
|
| 4-1. |
|
| 4-2. |
|
| 4-3. |
|
| 4-4. |
|
| |
|
|
|
 |
| 4.色を処方にする |
 |
| 1.色彩学の基礎知識で色を数値として表す色彩学について説明しましたが、実際に処方を予測するにはどうしたらよいのでしょうか?色剤を混ぜ合わせた場合、1-4.混色の種類で説明したような減法混色と呼ばれる複雑なメカニズムで色は変化しています。 |
 |
| 4-2.複数の色を混ぜる |
 |
色を吸収と散乱で表すことにより、複数の色剤の混合は層が複数あると解釈することができ、 反射率・三刺激値では無理であった減法混色での色予測が可能になります。
D.R.Duncanは吸光係数K・散乱係数Sに加成性が成り立つことを発見し、次の式を発表しました。
|
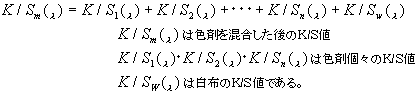 |
| この式は下地や白の色剤のS値が充分大きい場合の近似式で、本来の式はKとSは別々に積算されます。 |
| |
|
|
|
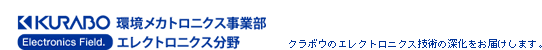




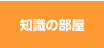

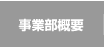
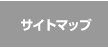
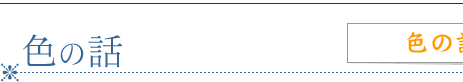

 プライバシーポリシー
プライバシーポリシー